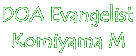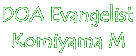|
|
|
|
 |
 見える化とは何か 見える化とは何か
最近IT業界では、可視化とか見える化とかが流行りのようだ。
よほど今まで何にも見えていなかったと言うことだろう。
履歴データを含め、基幹系のシステムを中心に情報系だのDWHだのと、ほとんどのデータが常駐する環境で、見えないものなど有るのかと思うが、どうやら見えないのはデータの所在のようだ。
散らかった部屋と同じで、有るにはあるのだが、何処に在るのか分からなければ無いも同じと言うことだ。
そちらは、データ管理をきちんとして貰うこととして、話を見える化に戻すとしよう。
さて、見える化とは可視化と同義語だと思っていたが、どうやら間違いの様だ。
少なくとも、業界用語としての見える化と言うのは、可視化が単に目に見えていれば良しとするのに対して、きちんと理解することまでを含んだ意味合いで使われているらしい。
つまり、データを提供する目的達成を見込んだ、一連の作業操作を見える化と表現するらしい。
データの提供までの仕組みが可視化だとすると、利用者や利用する状況に応じたカスタマイズを含むと言う事になる。
 見える化の仕組み 見える化の仕組み
利用者の理解を得ることが見える化の目的だとすると、そこには当然ながら、データの利用者からの情報要求に対して、データの提供側からの確認と言うか、コミュニケーションが必要になる。
何に使うの?、何を見たいの?、どこを見たいの?・・・・
ようするに5W2Hである。
最後のH(How much)は忘れがちだが、いくらまでのコストで見たいのと言う判断は大切だ。
良く、お偉方が訳も分からずに要求したデータを、コスト度外視で実現しようとするケースがあるが「そのために2000万円掛ると分かって言ってるんじゃないと思うぞ」と思う事は良くあるので、コストの確認は重要だ。
予断だが、このコスト意識の差が経営と情報システム部門の齟齬を引き起こす大きな原因の一つだと思う。
経営者は、情報システムが保守の繰り返しで、生産性が3〜4年で半分になる事など知らないので、10年も20年も続けて使っている情報システムの生産性について、全社の認識を合わせておく必要があるだろう。
ITガバナンスを言うなら、先ずは、保守性が急激に低下するようなシステムの作りから変えて行かなければいけない。
さて、またまた話を戻して、5W2Hだが、当然、同じデータを提供しても分かる人と分からない人が居る事になるが、ここが難しい所で、分からない人に対しては何処まで対応すれば良いかと言う事になる。
あいてが、お客さんやお偉方の場合、その対応が営業につながったり、自分の評価につながるのでついつい何処までも行ってしまいそうだが、ここは、企業レベルの視点で考える必要があるだろう。
つまらないデータの取得に法外なコストを掛けるような社員や経営者は、はっきり行って問題だろう。
提供されたデータを解釈して理解するための能力は、基本的には個人の努力で獲得し個人の判断で使うべき能力である。
その部分にデータ提供側の介入を許す事になると、提供されるデータに恣意性が入る危険性が生じてしまう。
 見える化の危険性 見える化の危険性
データの要求に大して客観的な数値などの提供は単なる可視化、相手にそのデータの解釈から理解すべき状況や傾向まで分からせる事を含めて見える化だとすると、データの解釈を行うのは誰かと言う事が問題だ。
この危険性を排除するには、データの利用に当たっては、利用者に一定の情報処理能力が必要となる。
つまり、5W2Hの確認に当たっては、目的とコストと効果と方法を調整し、必要ならデータ利用者の学習も含めて、最終的な目的達成への手順を検討すr必要があると言うことになる。
 まとめ まとめ
以上、可視化と違い、見える化は単に目で見えれば良いのでは無く、解釈・理解を含んだ、データを目的に沿って使えるように提供する仕組みなので、解釈理解の処理工程をデータ提供側に持って行ってしまうと、恣意性が介入する余地が出来る。
それは拙いので、データを利用する側も、利用のために何らかの前提知識や学習が必要なら、ちゃんと使えるように実践的な学習や経験をしておきましょうと言う事だ。
この部分は、情報処理の大半を外部委託するようになって以来、「その位自分でやれなきゃ給料は貰えないぞ」と、優しく指導してくれる情報システム部門が滅び、「それもこれも何でもやります」と言う委託先の担当者に囲まれていたのでは、コスト意識がマヒしていないか意識的に確認する必要がある。
如何なるデータ処理に対しても、そのデータの取得コストはと言う事と、それによる判断や行動の価値は幾らかと言う事は常に意識しておく必要がある。
ま、これは見える化に限らないが。
|
|
|