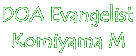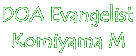このページでは、このデータベース設計基礎講座以外に、データベース設計の学習に役立つサイトを紹介している。
これだけの情報を、書籍で入手しようと思ったら、それだけで数万円の出費は覚悟しなければならないだろう。
況や、講義内容が理解出来るかどうかに関わらず、セミナーを受講すると、その費用は数十万になるはずだ。
全く、便利な世の中に成ったものである。
逆に言うと、この環境で「知りませんでした」は通用しないと言う事だろう。。
ここのお役立ち情報を活用して(もちろん中心はこのサイトに置いて欲しい)大いにスキルを磨き、決して、リレーションシップの無いER図を、臆面も無く、顧客に納品する事の無いようにして貰いたい。

お役立ちコラム
【データ項目名で分かるデータベース設計の拙さ】
当月、前月などと、データ項目名の修飾語に相対的期間表現を使う場合がある。
多くの場合、12カ月分を表形式で持ち、新たに一定期間が経過すると表をずらして新たな値を追加する更新処理を行う。
月別〜として、毎月処理年月(処理対象時期または期間)と一緒に追加しておけば、更新する必要はないものを、わざわざ更新を誘発する形式でデータを持っていると言う事になる。
おまけに、本来は月別〜と一つのデータ項目名で対応可能なものを、相対的期間表現で収束する事で、見かけのデータ項目名を増やしてしまう効果がある。
古いシステムのファイル設計に良く見られるが、その名称でユーザインターフェースに表示される事は無いので(もしあれば、全体時期に置き変えて表示すべき)、これらの名称を整理する事で、見かけのデータ項目数が削減される。